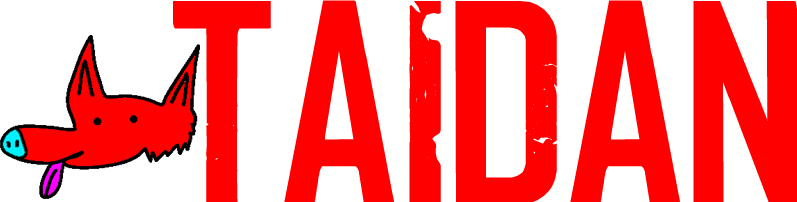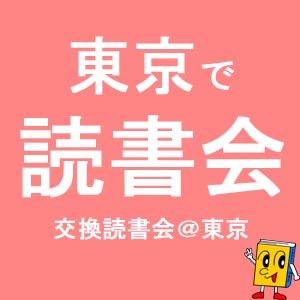「ニューミュージック~女性アーティストの時代の到来~」
公開日:
:
自分との対談(日記), 音楽 ウーマン, シンガーソングライター, ニューミュージック, 女性, 歌手, 社会, 進出
以下の本を読んでまとめた文章です。
「読むJ-POP」田家秀樹著(朝日新聞社)2004年
「フォークソング運動」 辻俊一郎著 (新風舎)2001年
「フォーク名曲事典300曲 ~バラが咲いたから悪女までの誕生秘話~」(ヤマハミュージックメディア) 2007年
「女性アーティストの時代」
吉田拓郎や井上陽水といった人物の登場により、日本の音楽史は進化していった。そうした中で、70年代中頃に「ニューミュージック」という言葉が登場する。
このニューミュージックと呼ばれるものの特長として、
- 演奏スタイルが華やかであること、
- 日本語の歌であること、
- 私的な世界を歌うこと、
- フォークやロックとは違い綺麗な衣装であること
- シンガーソングライターであること
そんな、ニューミュージックの主役は女性だった。
この時代は特に、男性中心の社会であり、女性が第一線で活躍するのは珍しかった。もちろん、女性の歌手はいたが、男性の作詞、作曲で歌っていたものがほとんどだった。たとえば、藤圭子の「新宿の女」や奥村チヨの「恋の奴隷」。これらは、男本位の歌だった。しかし、女性の社会的な立場も変わりつつあり、私たちの本当の歌がないとなる。
荒井由美
そこで、登場したのが荒井由美(松任谷由美)ことユーミンである。
彼女は、それまでのフォーク系のシンガー・ソングライターとは違ったコード進行で、独特な声。
さらに、独特なファション。
様々なものが今までと違っていた。
https://www.youtube.com/watch?v=fRqQMo12uYs
ユーミンは1972年「返事はいらない」でデビューする。
しかし、彼女の歌は全く売れなかった。なぜなら、彼女の新しさを受け入れる基盤が成り立っていなかったからだ。
ユーミン自身もこんなことを言っている。
「五輪真弓さんの歌は自分のことを考えながら歌にしているので、聴きながら考える音楽と言えるけれども、私のは全然ちがうのよ。聴きながら考えるっていうよりも、軽く聴けるというか、イージーリスニングかな。イージーリスニングといっても薄っぺらな意味ではなく、気持ちよく聴けるっていうのかな。」
彼女はそう語り、自分自身でも新しさに自信をもっていた。
五輪真弓
ユーミンがデビューしたのと同じ年にもう一人、女性シンガー・ソングライターの五輪真弓がデビューする。
彼女は、いきなりアルバム・デビューでしかもレコーディングは、海外で行い、当時、人気のキャロル・キングも参加していた。
(キャロルキングは、いまでも夜な夜な酒を飲みながら聞いている)
日本の女性アーティストが世界を創作の舞台としたという点でも画期的だった。
彼女の功績も忘れてはならないだろう。
中島みゆき
そして、1975年もう一人のシンガー・ソングライター中島みゆきが「アザミ嬢のララバイ」でデビューする。
中島みゆきはユーミンとは違い、過去のフォークソングなどからの影響がみられるそうだ。
とくに、吉田拓郎には強い影響を受けていて、実際、中島みゆきは「永遠の嘘をついてくれ」吉田拓郎に提供している。
しかし、中島みゆきの凄さは、彼女しか書くことのできない独特な詞を書けることだ。
そして、その結果としてオリコンで、4つの年代に渡ってシングルチャート1位を獲得している唯一のソロ・アーティストになったのではないか。(1970年代:わかれうた、1980年代:悪女、1990年代:空と君のあいだに、旅人のうた、2000年代:地上の星)
今では日本の音楽シーンでも女性のシンガー・ソングライターは珍しくないが、約30年前の出来事があったからこそだといえるだろう
おわり

みずしままさゆき を著作者とするこの 作品 は クリエイティブ・コモンズの 表示 4.0 国際 ライセンスで提供されています。
関連記事
-
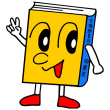
-
「読書会は、素晴らしき本たちとの出会いである~交換読書会を行っての感想をまとめてみた。その1~」
先日の3月14日に、僕が主催している「交換読書会」というものを久しぶりに行ったんですけど、そのときに
-
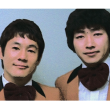
-
漫才の歴史は非常に奥深い~「たけしの“これがホントのニッポン芸能史”」より
はじめに 今年の3月にBSプレミアにて『たけしの“これがホントのニッポン芸能史”「漫才」』
-

-
「馬肉を食べて美味しかったよという、ただそれだけの話」~渋谷にあるロッキー馬力屋~
馬肉を食べたいという欲望 今年に入ってすぐの深夜2時すぎに馬肉を食べるというお知らせが入り、参加し
-

-
フットサル合コン、通称サルコンに行ってきた~サルコンは評判通りだった~
まくら(はじめに) 街コンが行われ始めたのは、いまから3~4年ぐらい前だと記憶する。たしか、ど
-

-
紀伊國屋のビブリオバトルに出てみた、その3。「テーマが、ガイマン」だったのでスターウォーズの本をたずさえて・・・
はじめに 最近は、「交換読書会」のサイトしか更新しておらず、このサイトでは久しぶりに投稿。
-

-
「イシス編集学校の編集術ワークショップに参加してきた~編集は楽しい~」
まくら(はじめに)~伝説の編集者、松岡正剛~ 千夜千冊というサイトをよく閲覧する。ここには、伝
-

-
「中野にある、”お笑いライブ スピン!”という誰でも出演できるLIVEに参加してみた」
スタンドアップ・コメディ あれは、たしか3月31日だった。 “お笑いライブ スピン”というものに出
-
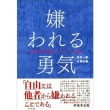
-
「嫌われる勇気」を読んで思ったこと、そして立川談志。
「嫌われる勇気」を読んで感じたことを以下に書いてみた。(とはいうものの、過去に違うブログで書いたもの
-

-
紀伊國屋のビブリオバトルに出てみた、その1。「ワイセツって何ですか?」(ろくでなし子著)をたずさえて・・・
ビブリオバトルとは いまから、1ヶ月ほど前の6月6日にビブリオバトルというものに参加した。ご存
-
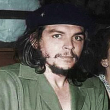
-
「最近話題のキューバ、そういえば!!と思いだして、チェ・ゲバラのお話」
まくら(はじめに) 2014年12月17日に、オバマ大統領がキューバとの国