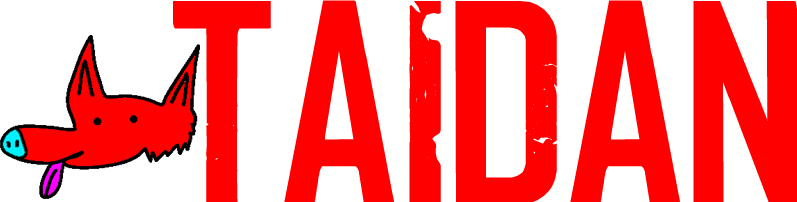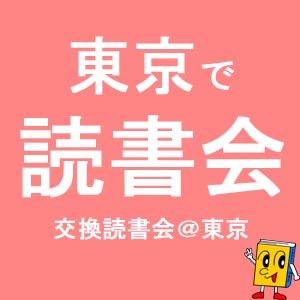本目さよさんとの対談をして考えたこと(クォータ制とか烏合の衆とか!?)
(本目さよさんありがとうございました!!)
本目さよさんとの対談をして考えたこと
最近のブームなのか、稚拙な地方議員が続出している。セクハラ野次議員に始まり、泣き叫び議員、穴あきコンドーム大好き議員、そしてそれが明るみになったきっかけでもあるブログを議員が行うことを規制しようとした肥溜めのような糞議会。その他にも、20人中15人が逮捕された・・・・・なんていうのもあったか。
これらのことは、たまたま同時多発的に起こったことなのだろうか。まだまだ、目にみえぬことがあることは自明なことだ。
しかしながら、この議員、そしてそれらが運営する議会という悪しき世界を産んでしまったのは、ぼくたちのこの手だ。その手を動かす脳は、いったいどのような判断でそうしてしまったのかいま一度考えなくてはならないだろう。
その考える材料(そうしてしまったこと)として、現在の選挙で頼りになるのが、恐らくポスターだ。そこで描かれているニコニコとした偽善的な笑顔やそれを際立たせるキャッチコピーや色使いといったファンタジーにより大方の人は投票する人を決めているはずだ。その他には、昔ながらの付き合いなどだろう。
ぼくの考えとしては、地方レベルの議員であれば、半分は投票で決めてもう半分はそこに住んでいる人から裁判員制度のように無作為に選べばいいと思っている。理由としては、昨今の投票率の低さからも自明なように、無理矢理でもそうしないと、一般の人が政治に興味を抱かないからであると同時に、地方レベルの議員は、例外を除いてどんな人でもなれるからである。それは、あの号泣議員やコンドーム穴あき大好き議員が出来ていたのだからほとんどの人がとりあえずは、大丈夫だろう。
だが、99%そのような仕組みになるはずはない。既得権益という病魔に取りつかれ、権力という甘い蜜を守りたい烏合の衆が無数に蔓延っているからである。だから、その烏合の衆たちをいかに味方につけるかがいいのではないだろうか。
と、前置きは長くなったが、このように実感したのは、本目さんとの対談の中で、女性議員の少なさの話題が上がったことからである。その少なさにより、女性故の悩みは、しばし理解されないことがあるようだ。諸外国ではクォータ制を導入し、男女の比率がほぼ同じになるよう調整しているところもある。
スウェーデンは,1991年の選挙で,女性議員の割合が減少したことから,政党が選挙名簿におけるクォータ制を導入し,その後の選挙において女性議員が大幅に増加することとなった。スウェーデンにおいては,女性自身の政治への参画意識が高く,女性の政治参画を促す社会的な環境が整備されていたことから,クォータ制が大きな効果を発揮したといえる。
ドイツでは,主要政党がクォータ制を導入し始めた1980年代後半以降,着実に女性議員が増加した。それまでも,各政党において党内の女性の地位向上に関して取組が進められていたが,はかばかしく進展しなかったことから,事前に詳細な検討が行われた後,クォータ制が最終的な手段として導入されており,女性の政治参画への気運は高まっていたといえる。
二大政党制のイギリスでは,女性政策が選挙の争点の一つとなっており,1990年代に入って,労働党が様々な方法でクォータ制を導入したことから,1992年から1997年にかけて,女性議員数が60人から120人へと倍増した。
韓国は,日本と同様に女性議員の割合が低い状況にある。2000年の第16代選挙の前に政党法を改正し,比例代表選挙名簿の30%を女性とする割当制を導入したことから,16代選挙では女性議員が9人(3.0%)から16人(5.9%)へ増加したが,依然として低い数値にとどまっている。また,1987年の民主化宣言以降,各政党は女性の地位向上のための施策を打ち出し,1992年の第14代大統領選挙以降,女性の政治参画の拡大の支援が公約とされるなど女性の政治参画への意識の高まりがみられる。また,1995年に制定された女性発展基本法においても,女性の政治への参画の拡大に対する政府の支援を明記しており,このような変革の波が政党法の改正につながっている
明らかに女性議員の少ない日本は、直ちに、このクォータ制を導入すべきだと思うが、先ほど言った、既得権益に群がり権力という蜜を守りたい烏合の衆は、そうはさせないだろう。そのため、その烏合の衆をいかに味方につけるかが重要なのだ(クォータ制は地方議会レベルの話ではないが、これを地方の問題などに置き換えればいいだろう)。と、同時にそれはとても悲しいことである。このような回りくどい方法をしなければ変わらないのだろうか。
1つだけあるとしたら、しっかりとした判断で投票することしかない。その極めて抽象的なしっかりとした判断という言葉だが、これは、投票したからお前に任せるという考えではなく、投票した人と一緒に社会を変えていくというような考えでなくてはいけないだろう。
一緒に変えていく、それは、地方がよりよくなるよう変える、悪くならないよう守る、その主役は、ぼくたちであり、ぼくたちの住むこの社会だからだ。
そのための代行があくまで議員の存在なのではないか。故に、一緒に考えそして、利他的に動いてくれる議員を選ばなくてはならない。
だが、その判断材料になる資料が極めて少ないのが地方の問題だろう。それ故に偽善性に満ち溢れたポスターで判断してしまう。そうならないためにも、ぼくのこの対談動画が少しでも役立てばと思う次第だ。
というように、この活動に正当性を持たせてみたが、ぼく自身は政治というものにそんなに興味はない。ちゃぶ台返しをして終わり。この話はまたどこかで。
おわり
「私が政治へと向かった理由、そして政治の世界へ」【No.8-1本目さよ(台東区区議,民主党)】
「子育てがしやすい社会に、投票率の低い若者へ」【No.8-2本目さよ(台東区区議,民主党)】
「セクハラ問題から考える女性議員の立場の弱さ、そして理想の社会は!?」【No.8-3本目さよ(台東区区議,民主党)】

みずしままさゆき を著作者とするこの 作品 は クリエイティブ・コモンズの 表示 4.0 国際 ライセンスで提供されています。
関連記事
-

-
本目さよ(台東区議)「女性議員の私が、政治を目ざした理由」【No.8】(書き起こし済み)
本目さよ【台東区議民主党】(http://www.sayohomme.co